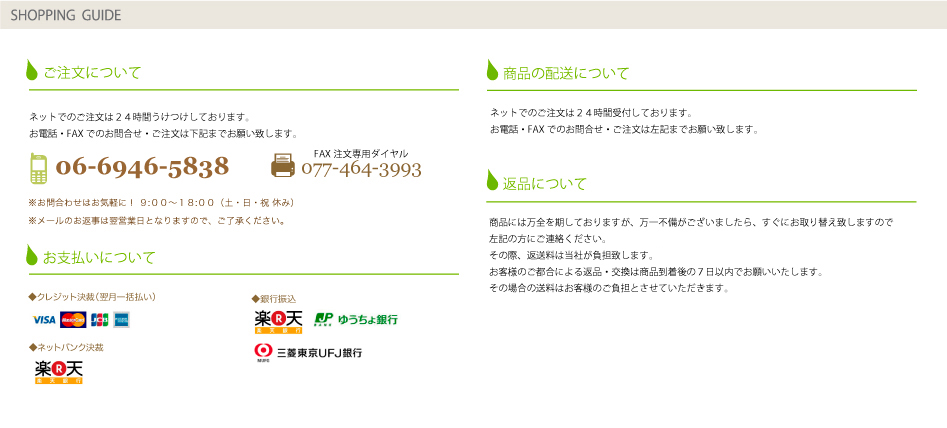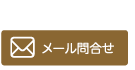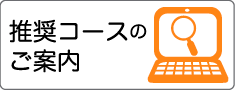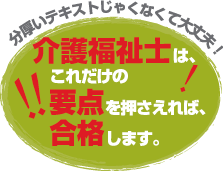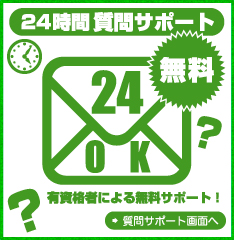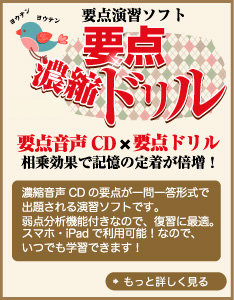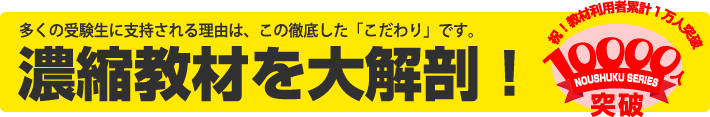

|
速聴CDとは、通常音声を倍の速度で収録した音声CDです。通常盤は内容把握の為にも、少しゆっくりしたテンポで収録しております。速聴CDは、その後の何度も聴いて記憶していく過程で大変有効になります。そうすることで、通常の復習時間を短い時間で切り上げることはもちろん、脳が活性化される効果もあるので、効率よく学習することができます。 濃縮!介護福祉士の学習効果を最大限に引き出すためにも、是非「速聴CD」をセットでお申し込み頂くことをお勧めします! |
・ |
教材業界ではあり得ないサービスのひとつである「濃縮!!教材の安心サポート」。 濃縮介護福祉士の「安心サポート」はすべての商品に安心保証付いています。 サポート内容は、リスニングCDを破損された場合、または傷つき正常に再生できない場合はご連絡いただければ購入から2年間以内であればすぐに新しい商品とお取替えいたします。 CDを屋外に持ち出す機会の多い方は、特に安心いただけるサービスとなっております。皆様に、なんとか介護福祉士試験に合格していただきたい!そんな思いが詰まった真心サービスです。 |
濃縮!介護福祉士<収録分野>
1、人間の尊厳と自立
●1、人間の尊厳と自立
1-1、人間の理解と尊厳
●2、介護における尊厳の保持自立支援
2-1、人権と尊厳
2、人間関係とコミュニケーション
●1、人間関係の形成
1-1、人間関係と心理
●2、コミュニケーションの基礎
2-1、対人関係とコミュニケーション 2-2、コミュニケーションを促す環境 2-3、コミュニケーションの技法 2-4、道具を用いた言語的コミュニケーション
3、社会の理解
●1、生活と福祉
1-1、家庭生活の基本機能 1-2、家族 1-3、地域 1-4、社会組織 1-5、ライフスタイルおよび社会構造の変化 1-6、生活支援と福祉
●2、社会保障制度
2-1、社会保障の基本的な考え方 2-2、日本の社会保障制度の発達 2-3、日本の社会保障制度のしくみの基礎的理解 2-4、現代社会における社会保障制度
●3、介護保険制度
3-1、介護保険制度創設の背景及び目的 3-2、介護保険者と被保険者 3-3、介護保険の保険給付と利用者負担 3-4、介護保険制度の費用等 3-5、受給権者 3-6、介護サービス利用までの流れ
●5、障害者総合支援法(旧障害者自立支援制度)
5-1、障害者総合支援法制度創設の背景及び目的 5-2、障害者総合支援法の目的 5-3、障害者基本計画新障害者プラン 5-4、障害福祉サービスの種類内容 5-5、費用負担 5-6、利用の流れ
●6、障害者総合支援制度における組織、団体の機能と役割
6-1、国都道府県市町村の責務
●7、障害者に対するその他の施策
7-1、障害者施策 7-2、障害児施策 7-3、知的障害者施策 7-4、精神障害者施策 7-5、母子保健 7-6、特別支援教育 7-7、所得保障経済負担の軽減 7-8、雇用就労
●8、介護実践に関連する諸制度
8-1、個人情報保護に関する制度 8-2、成年後見制度 8-3、苦情解決 8-4、消費者保護法 8-5、高齢者虐待防止法
●9、保健医療福祉に関する施策の概要
9-1、生活習慣病予防と健康づくり 9-2、高齢者医療制度と特定健康診査等 9-3、結核感染症対策 9-4、難病対策 9-5、介護と関連領域との連携に必要な法規 9-6、高齢者障害者の住生活 9-7、生活保護制度の慨要
4、介護の基本
●1、介護福祉士を取り巻く状況
1-1、介護の歴史
●2、介護福祉士の役割と機能を支えるしくみ
2-1、社会福祉士及び介護福祉士法 2-2、専門職能団体の活動
●3、尊厳を支える介護
3-1、尊厳を支えるケア
●4、自立に向けた介護
4-1、自立支援 4-2、ICF 4-3、リハビリテーション
●5、介護を必要とする人の理解
5-1、人間の多様性複雑性の理解 5-2、障害のある人のくらしの理解 5-3、介護を必要とする人の生活環境の理解
●6、介護サービス
6-1、介護サービスの概要 6-2、居宅系サービス(高齢者) 6-3、入所サービス(高齢者) 6-4、障害者居宅系サービス 6-5、障害者入所系サービス
●7、介護実践における連携
7-1、多職種連携(チームアプローチ) 7-2、地域連携
●8、介護従事者の倫理
8-1、職業倫理
●9、介護における安全の確保とリスクマネジメント
9-1、介護における安全の確保 9-2、事故防止、安全対策 9-3、感染対策
●10、介護従事者の安全
10-1、介護従事者の心身の健康管理 10-2、身体の健康管理
5、コミュニケーション技術
●1、介護におけるコミュニケーションの基本
1-1、介護におけるコミュニケーションの意義、目的、役割 1-2、利用者家族との関係づくり
●2、介護場面における利用者家族とのコミュニケーション
2―1、利用者家族とのコミュニケーションの実際 2-2、利用者の状況状態に応じたコミュニケーションの技法の実際
●3、介護におけるチームのコミュニケーション
3-1、記録による情報の共有化、報告、会議
6、介護過程
●1、介護過程の意義
1-1、介護過程の意義、目的目標
●2、介護過程の展開
2-1、情報収集とアセスメント 2-2、課題、目標 2-3、計画、実施、評価
●3、介護過程の実践的展開
3-1、介護展開の実際
●4、介護過程とチームアプローチ
4-1、介護過程とチームアプローチ
7、生活支援技術
●1、生活支援
1-1、生活の理解 1-2、生活支援 1-3、生活支援と介護予防 1-4、生活支援と福祉用具の活用
●2、自立に向けた居住環境の環境
2-1、居住環境のアセスメント 2-2、安全で心地よい生活の場づくり 2-3、施設等での集住の場合の工夫留意点
●3、自立に向けた身じたくの介護
3-1、整容行動、衣生活を調整する能力のアセスメントと介助の技法 3-2、衣服の着脱 3-3、利用者の状態、状況に応じた身じたくの介助の留意点
●4、自立に向けた移動の介護
4-1、移動に関するアセスメント 4-2、安全で気兼ねなく動けることを支える介護 4-3、安全で的確な移動移乗の介助の技法 4-4、歩行の介助 4-5、利用者の状態状況に合わせた移動介助の留意点
●5、自立に向けた食事の介護
5-1、食事の意義と目的 5-2、安全で的確な食事介助の技法 5-3、利用者の状態、状況に応じた介助の留意点
●6、自立に向けた入浴清潔保持の介護
6-1、入浴の意義、目的とアセスメント 6-2、安全で的確な入浴清潔保持の介助の技法 6-3、機械浴シャワー浴足浴手浴洗髪清拭 6-4、利用者の状態状況に応じた介護の留意点
●7、自立に向けた排泄の介護
7-1、排泄の意義目的 7-2、排泄に関する利用者のアセスメント 7-3、気持ちよい排泄を支える介護 7-4、安全で的確な排泄の介助の技法 7-5、トイレ.ポータブルトイレ 7-6、採尿器差し込み便器 7-7、おむつ 7-8、利用者の状態状況に応じた介助の留意点 7-9、職種の役割と協働
●8、自立に向けた家事の介護
8-1、家事に関する利用者のアセスメント 8-2、家事の介助の技法 8-3、食中毒の予防 8-4、調理の基本 8-5、服生活の基本 8-6、洗濯 8―7、衣類寝具の衛生管理 8―8、掃除 8-9、買い物 8-10、家庭経営、家計の管理
●9、自立に向けた睡眠の介護
9-1、睡眠の意義目的アセスメント 9-2、安眠の為の介護 9-3、利用者の状態状況に応じた介助の留意点
●10、終末期の介護
10-1、終末期における介護の意義と目的 10-2、医療との連携 10-3、終末期の介護臨終時の対応 10-4、グリーフケア
●11、緊急時の対応
11-1、外傷 11-2、骨折打撲 11-3、熱傷 11-4、呼吸困難呼吸停止誤嚥 11-5、応急処置
8、発達と老化の理解
●1、人間の成長と発達の基礎的理解
1-1成長と発達
●2、老年期の発達と成熟
2-1、老年期の定義 2-2、老年期の発達課題
●3、老化に伴うこころとからだの変化と日常生活
3-1、老化に伴う心身の変化の特徴 3-2、心身の機能の変化 3-3、高齢者の心理
●4、高齢者と健康
4-1、高齢者の疾病と生活上の留意点 4-2、高齢者の骨関節 4―3、高齢者のめまい 4-4、しびれ 4-5、浮腫(むくみ) 4-6、咳痰 4-7、息切息苦しさ 4-8、そう痒感(かゆみ) 4-9、その他の特徴
●5、高齢者に多い病気とその日常生活上の留意点
5-1、脳血管障害 5-2、高血圧 5-3、糖尿病 5-4、ガン 5-5、心疾患 5-6、その他の生活習慣病 5-7、眼病 5-8、耳の病気 5-9、泌尿器の病気 5-10、消化器系疾患 5-11、薬剤の知識
9、認知症の理解
●1、認知症を取り巻く状況
1-1、認知症ケアの歴史 1-2、認知症ケアの理念 1-3、認知症高齢者の現状と今後
●2、医学的側面から見た認知症の基礎
2-1、認知症障害 2-2、認知症と間違えられやすい症状
●3、認知症の原因となる主な病気の症状の特徴
3-1、アルツ八イマー病(AD) 3-2、脳血管疾患 3-3、レビー小体病 3-4、ビック病(前頭側頭型認知症) 3-5、クロイツフェルトヤコブ病 3-6、慢性硬膜下血腫 3-7、若年認知症 3-8、病院検査と治療
●4、認知症に伴うこころとからだの変化と日常生活
4-1、認知症の特徴的心理行動
●5、家族支援
5-1、家族支援
10、障害の理解
●1、障害の基礎的理解
1-1、障害の概念 1-2、障害者福祉の基本理念
●2、医学的側面の基礎的知識
2-1、視覚障害 2-2、聴覚障害、言語機能障害 2-3、肢体不自由 2-4、内部障害 2-5、精神障害 2-6、高次脳機能障害の種類と原因と特性 2-7、知的障害 2-8、発達障害 2-9、難病 2-10、障害者の心理
●3、連携と協働
3-1、地域におけるサポート体制とチームアプローチ
●4、家族への支援
11、こころとからだのしくみ
●1、こころのしくみの理解
1-1、人間の欲求の基本的理解 1-2、自己概念と尊厳 1-3、こころのしくみの基礎
●2、からだのしくみの理解―からだのしくみの基礎-
2-1、心身の調和 2-2、生命の維持恒常のしくみ 2-3、脳神経 2-4、骨筋肉 2-5、感覚器 2-6、呼吸器 2-7、消化器 2-8、泌尿器、生殖器内分泌 2-9、循環器 2-10、血液リンパ 2-11、関節可動域
●3、身支度に関連したこころとからだのしくみ
3-1、身支度に関連したこころとからだの基礎知識 3-2、身じたくに関連したこころとからだのしくみ 3-3、機能の低下障害に及ぼす整容行動への影響
●4、移動に関連したこころとからだのしくみ
4-1、移動に関連したこころとからだの基礎知識 4-2、移動に関連したこころとからだのしくみ 4-3、機能の低下障害が及ぼす影響 4-4、生活場面におけるこころとからだの変化の気づきと医療職との連携
●5、食事に関連したこころとからだのしくみ
5-1、食事に関連しこころとからだの基礎知識 5-2、食べる事に関連したこころとからだのしくみ 5-3、機能の低下障害が及ぼす食事への影響 5-4、生活場面におけるこころとからだの変化の気づきと医療職との連携
●6、入浴、清潔保持に関連したこころとからだのしくみ
6-1、入浴、清潔保持に関連したこころとからだの基礎知識 6-2、清潔保持に関連したこころとからだのしくみ 6-3、機能低下障害が及ぼす入浴、清潔保持への影響 6-4、生活場面におけるこころとからだの変化の気づきと医療職との連携
●7、排泄に関連したこころとからだのしくみ
<排泄に関連したこころとからだの基礎知識>
7-1、尿の性状、量、回数、生成のしくみ 7-2、便の性状、量、回数、生成のしくみ
<排泄に関連したこころとからだのしくみ>
7-3、排尿排便のしくみ
<機能の低下障害が及ぼす排泄への影響>
7-4、失禁等 7-5、便秘 7-6、下痢 7-7、生活場面におけるこころとからだの変化の気づきと医療職との連携
●8、睡眠に関連したこころとからだのしくみ
8-1、睡眠に関連したこころとからだの基礎知識 8-2、睡眠に関連したこころとからだのしくみ 8-3、機能の低下障害が及ぼす睡眠の影響 8-4、生活場面におけるこころとからだの変化の気づきと医療職との連携
●9、死にゆく人のこころとからだのしくみ
9-1、死の捉え方
<終末期から危篤、死亡時のからだの理解>
9-2、身体の機能の低下の特徴 9-3、死後の身体的変化 9-4、死に対するこころの理解
<医療職との連携>
9-5、医療の実際と介護実際
●1、医療的ケア実施の基礎
1-1、人間と社会
1-2、医療保険制度とチーム医療
1-3、安全な療養生活
1-4、清潔保持と感染予防
1-5、健康状態の把握
●2、喀痰吸引
2-1、高齢者及び障害児・者の喀痰吸引の基礎的知識
2-2、高齢者及び障害児・者の喀痰吸引の実施手順
●3、経管栄養
3-1、高齢者及び障害児・者の経管栄養の基礎的知識
3-2、高齢者及び障害児・者の経管栄養の実施手順
| 藤本 たかし さん | |
 |
|
| 国広 稔 さん(掲載仮名) | |
 |
|
| 伊坂 幸嗣 さん | |
 |
|
| 上山 明子 さん | |
 |
|
| 藤本 さん | |
 |
|
| 神田 紀子 さん | |
 |
|
| 藤高 政人 さん | |
 |
|
| 川野 健 さん | |
 |
|
| 田中 静子さん | |
 |
|
| 田中 あい さん | |
 |
|
| 松川 文乃 さん | |
 |
|
| 中田 千裕 さん | |
 |
|
| 神道 裕美 さん | |
 |
|
| 金坂 さん | |
 |
|
| 島田 千穂 さん | |
 |
|
| 黒田歩さん | |
 |
|
| 田辺 直輝 さん | |
 |
|
| 滝沢 まなみ さん | |
 |
|
| 手塚 正男 さん | |
 |
|
| 河野 亜紀 さん | |
 |
|